| 閉じる |
| 【考案の名称】網付き鍋 【実用新案権者】 【識別番号】523068684 【氏名又は名称】細井 章年 【住所又は居所】神奈川県横浜市磯子区滝頭2-37-13 【代理人】 【識別番号】100140866 【弁理士】 【氏名又は名称】佐藤 武史 【考案者】 【氏名】細井 章年 【住所又は居所】神奈川県横浜市磯子区滝頭2-37-13 【要約】 (修正有) 【課題】より簡単に湯切りをするとともに、湯切り後の麺類の盛り付けが容易に可能な網付き鍋を提供すること。 【解決手段】網付き鍋1は、鍋本体11と、鍋本体11の上部に回動自在に取り付けられ、鍋本体11の開口を被う閉状態と鍋本体11の側方に配置される開状態とに切り替え可能な網かご体を有する網部30と、を備え、麺類を茹でた際に網かご体を閉状態とし、鍋本体11を傾けて網かご体を介して鍋本体11内の湯を放出することにより、湯切りを容易に行うことができるとともに、網かご体に麺類を盛り付けることが可能になる。 【選択図】図2 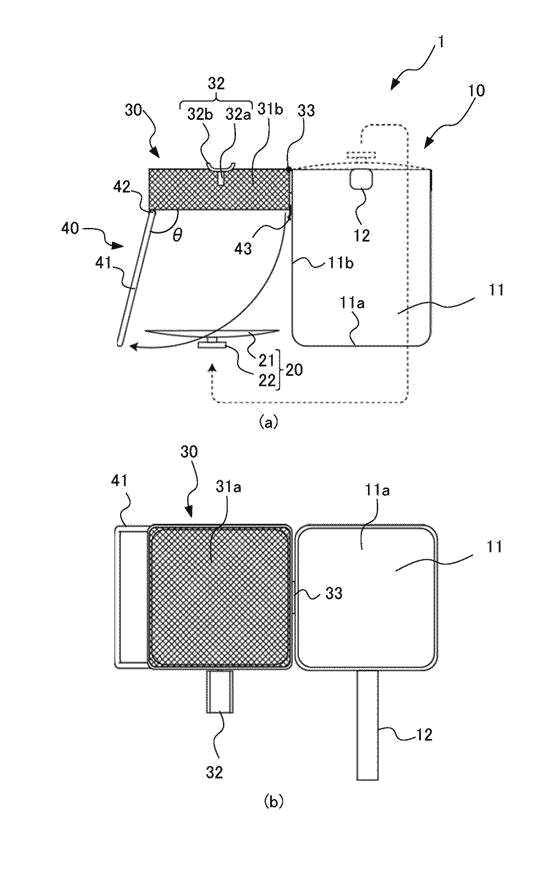 【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 鍋本体と、 当該鍋本体の上部に回動自在に取り付けられ、前記鍋本体の開口を被う閉状態と前記鍋本体の側方に配置される開状態とに切り替え可能な網体と、を備えることを特徴とする網付き鍋。 【請求項2】 前記網体は、前記閉状態において上方に膨出していることを特徴とする請求項1記載の網付き鍋。 【請求項3】 前記網体に回動自在に取り付けられ、前記網体から下方に延びて前記開状態の前記網体を支持する脚体を更に備えることを特徴とする請求項1又は2記載の網付き鍋。 【考案の詳細な説明】 【技術分野】 【0001】 本考案は、網付き鍋に関する。 【背景技術】 【0002】 従来、麺類を茹でる際に使用する鍋として、特許文献1に記載された麺類ゆで鍋がある。特許文献1に記載された鍋は、鍋の中で、パスタ等の麺類を入れてゆであげ、その後に水きりをするザルにおいて、鍋の中でお湯の循環対流を妨げないように、ザルの上面部が水面より沈む構造にしたものである。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0003】 【特許文献1】 特開2001−128845号公報 【考案の概要】 【考案が解決しようとする課題】 【0004】 特許文献1に記載の技術のように、鍋の中に、片手で支持する支持部を有するザルを入れ、そのザルの中に麺を入れて茹でることが従来から行われている。しかし、茹でた麺を実際に食べるまでには、更に作業が必要となる。例えば、蕎麦を茹でた場合には、蕎麦をザルに入れて湯切りをする工程と、ザルに入った蕎麦を水に晒す工程と、水に晒した蕎麦を蕎麦用のザルに盛り付ける工程を経ることになる。 【0005】 本考案は、このような問題点を解決し、麺類を茹でた際に、より簡単に湯切りをするとともに、湯切り後の麺類の盛り付けが容易に可能な網付き鍋を提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0006】 前記目的を達成するため、本考案は、次の構成を備えている。 【0007】 (1) 鍋本体(例えば、鍋本体11)と、 当該鍋本体の上部に回動自在に取り付けられ、前記鍋本体の開口を被う閉状態と前記鍋本体の側方に配置される開状態とに切り替え可能な網体(例えば、網かご体31)と、を備えることを特徴とする網付き鍋。 【0008】 (1)によれば、鍋本体の上部に網体が開閉自在に設けられ、網体が鍋本体の開口を被う閉状態と、網体が鍋本体の側方に位置付けられる開状態と、に切り替えることが可能になる。これにより、閉状態とすることによって鍋本体に入っている湯を、網体を介して放出することが可能になり、茹でた麺類をこぼすことなく湯切りをすることが可能になる。しかも湯切り後の鍋本体の麺類を網体に移して開状態にすることによって、網体に麺類を盛り付けることが容易に可能になる。このように、麺類を茹でた際に、より簡単に湯切りをすることが可能になり、湯切りの後の麺類を網体に容易に盛り付けることが可能になる。 【0009】 (2) (1)において、前記網体は、前記閉状態において上方に膨出していることを特徴とする網付き鍋。 【0010】 (2)によれば、網体は、鍋本体を被った閉状態において上方に膨出しているため、湯切りをした後、網体が鍋本体の上方を被った閉状態を維持しながらひっくり返すことにより、麺類を網体に移動させるとともに、麺類を網体にそのまま保持させることが可能になる。このように、麺類を網体に移動させる際に、麺類がこぼれにくくなる。 【0011】 (3) (1)、(2)において、前記網体に回動自在に取り付けられ、前記網体から下方に延びて前記開状態の前記網部を支持する脚体(例えば、脚体41)を更に備えることを特徴とする網付き鍋。 【0012】 (3)によれば、脚体を回動させることにより、脚体が開状態にある網体を支持することが可能になる。このため、使用者は、網体に入っている蕎麦を食することが可能になる。 【0013】 【考案の効果】 【0014】 本考案によれば、麺類を茹でた際に、より簡単に湯切りをするとともに、湯切り後の麺類の盛り付けが容易に可能な網付き鍋を提供することができる。 【図面の簡単な説明】 【0015】 【図1】本考案の一実施形態における網付き鍋1の初期状態を示す説明図である。 【図2】図1の初期状態から、網付き鍋1の網かご体31を開いた状態を示す説明図である。 【考案を実施するための形態】 【0016】 本考案の一実施形態における網付き鍋について、図面を参照しながら詳細に説明する。 【0017】 図1は、本考案の一実施形態における網付き鍋1の初期状態を示す説明図であり、図1(a)は側面図、図1(b)は平面図である。 【0018】 網付き鍋1は、鍋部10と、鍋蓋20と、網部30と、脚部40と、を備えている。 【0019】 鍋部10は、鍋本体11と、把手12と、を有する。鍋本体11は、直方体形の金属製の容器体であり、正方形の底面部11aと、底面部11aの4辺から直角方向に延び、底面部11aの周囲を囲む壁面部11bと、を有する。把手12は、棒状部材からなり、一端部が、一の壁面部11bの上部中央に固定され、鍋本体11から遠ざかる方向に延びており、他端部が使用者によって把持される。 【0020】 鍋部10の上端部には、1段の段差が形成されており、上端面とこの上端面より低い位置に形成された正方形の環状の段差面とを備えている。 【0021】 鍋蓋20は、平面視正方形の金属板からなり、中央部が上方に若干膨出している蓋体21と、蓋体21の中心部に固定され、上方に向かって太くなる四角錐形状の取っ手22と、を有する。鍋蓋20は、鍋本体11の上端部に載置され、鍋部10の開口を開閉するものであり、蓋体21の外周部を鍋本体11の上端部の段差面上に当接させることにより、鍋部10の開口が閉鎖される。鍋蓋20が鍋本体11の上端部に載置されたとき、蓋体21の外周部の上面は鍋本体11の上端面よりも低い位置に位置付けられる。すなわち、蓋体21の外周部が鍋部10の上端面から突出しないように設計されている。 【0022】 網部30は、網かご体31と、網把手32と、ヒンジ33と、を備えている。網かご体31は、金属網からなり、正方形の底面部31aと、底面部31aの4辺から直角方向に延び、底面部31aの周囲を囲む壁面部31bと、を有する直方体形に構成されている。底面部31aは、平面視した場合に、鍋本体11の上端面の外周形状と略同じである。壁面部31bの高さは、側面視した場合に、鍋本体11の壁面部11bの高さよりも低い、横長の長方形である。網かご体31は、初期状態において、壁面部31bの先端を下方に向けて、壁面部31bの先端を鍋本体11の上端面に当接させることにより、鍋本体11の上に載置される。この際、網かご体31は、鍋本体11の開口を被った状態(閉状態)で上方に膨出しており、底面部31aが鍋部10の上端面よりも上方に位置付けられる。 【0023】 鍋本体11の高さは、網かご体31の高さよりも大きく設定されている。本実施形態によれば、鍋本体11の高さは、壁面部31bの横長の長方形形状における縦の長さよりも大きく、縦と横の長さの和よりも小さく設定されている。 【0024】 網把手32は、斜め方向に延びる延在部32aと、使用者が把持する把持部32bと、を備えている。 【0025】 延在部32aは、一端部が、一の壁面部31bの先端部中央に固定され、網かご体31から斜め方向に遠ざかるように延びており、他端部に把持部32bが固定される。把持部32bは、網部30の底面部31aを下方に、壁面部31bの先端部を上方に向けた場合に、壁面部31bの先端部よりも上方に位置付けられる。 【0026】 把持部32bは、長手方向に対して垂直方向の断面が略コ字形の棒状部材からなる。把持部32bは、把手12よりも短く形成されており、初期状態において、把手12の付け根部分の上部を囲むように配置される。 【0027】 ヒンジ33は、鍋本体11に網把手32を回動自在に連結するものである。ヒンジ33は、任意の位置に設けることができるが、図に示す例では、網把手32が固定された壁面部31bに直交する壁面部31bの先端部の中央部と、把手12が固定された壁面部11bに直交する壁面部11bの上端部の中央部と、を連結する。これにより、使用者が、把手12が自分の方に延びる方向に網付き鍋1を配置した場合、網把手32を把持して、上方に移動させることにより、網かご体31を、自分の方に延びる軸を中心に回動させることで、鍋本体11と網かご体31とを左右方向に配列した状態にすることができる。のちになお、網かご体31は、180°回転させた場合に、壁面部31bが鍋本体11の壁面部11bの上部に当接するため、それ以上の回動は規制されて、鍋本体11の上部の側方に配置される。 【0028】 脚部40は、底面部31aの外縁部に沿って、円柱状の金属棒をC字状に曲げを施してなる脚体41と、網部30に固定され、脚体41の両端部を回動自在に支持する円筒状の軸受部42、42と、止め金具43と、を備えている。 【0029】 軸受部42、42は、底面部31aにおける網把手32が固定された壁面部31b側の縁部の両端部に固定されている。軸受部42、42に脚体41の両端部を挿入することによって、脚体41が網かご体31に回動自在に取り付けられる。また、軸受部42、42は、脚部40の回動角度が90°を越えた所定角度θ(90°<θ<180°)になった場合に、脚部40の回動を規制するストッパを備えている。所定角度θは、鍋本体11の高さをH、網部30の高さをh、脚部40の一辺の長さをLとした場合に、Lcosθ=H−hの関係が成り立つように設定される。 【0030】 止め金具43は、金属板を湾曲させてなる板バネ部材からなる。止め金具43は、網把手32が固定された壁面部31bに対向する壁面部31bの先端部の中央に設けられており、脚体41の中央部に係合する。脚体41の中央部が止め金具43に係合した状態において、脚体41は底面部31aの外周部に位置付けられる。 【0031】 図2は、図1の初期状態から、網付き鍋1の網かご体31を開いた状態を示す説明図であり、図2(a)は側面図、図2(b)は平面図である。 【0032】 図1に示す初期状態において、使用者が網把手32を持って180°回動させることにより、図2に示すように、網かご体31は、鍋本体11の側方に位置付けられる。このように、網かご体31が、鍋本体11の上部に回動自在に取り付けられているため、図1に示すように、網かご体31が鍋本体11の開口を被う閉状態と、網かご体31が鍋本体11の開口から離間して鍋本体11の側方に配置される開状態とに切り替え可能になる。 【0033】 網かご体31を開状態にして、止め金具43に係合した状態にある脚体41を、止め金具43から外して回動させることにより、図2に示すように、脚体41が網かご体31の外側に向かって斜め下方に延びる。このため、脚体41の中央部をテーブル面に当接させることが可能になり、網かご体31の網把手32側の端部が脚体41によって支持される。これにより、開状態にある網かご体31を安定させることが可能になる。また、開状態において、脚体41の中央部と鍋本体11との距離が、鍋蓋20の長さより大きくなるため、網かご体31の下方のテーブル面に鍋蓋20を配置することが可能になる。 【0034】 図2に示す開状態において、網かご体31の底面部31aが壁面部31bの下方に位置付けられ、壁面部31bの先端部が上方を向いているため、網かご体31の内部に物体を載置することが可能になる。ここで、脚体41を回動させて、網かご体31を支持させることにより、網かご体31の内部に物体を載置した場合に、その重みによって鍋本体11が倒れてしまうことを防止することができる。 【0035】 次に、網付き鍋1の使用方法について説明する。ここでは一例として、蕎麦を茹でる手順について説明する。 【0036】 まず、鍋本体11に水を入れた後、図1に示すように、鍋蓋20を鍋本体11に載せ、更に、網かご体31を載せた状態で、網付き鍋1を火にかける。なお、鍋蓋20は必要に応じて使用する。水が沸騰した後、網かご体31を開き、鍋蓋20を外して、鍋本体11に蕎麦を入れて網かご体31を閉じる。 【0037】 そして、蕎麦が茹で上がった後に、使用者は、把手12と把持部32bとを同時に保持して、流し台に鍋本体11を移動させ、鍋本体11を傾けて網かご体31から鍋本体11内の湯を放出する。このように湯切りを行った後、鍋本体11に水を入れ、蕎麦を水に晒して、同様に鍋本体11を傾けて網かご体31から鍋本体11内の水を放出する。 【0038】 次に、把手12と把持部32bとを同時に保持して、鍋本体11と網かご体31とをひっくり返すことにより、蕎麦を網かご体31に移動させる。そして、この状態を維持しながら鍋本体11を回動させて網かご体31の側方に鍋本体11を位置付けて、鍋本体11をテーブルに載せる。このとき、網かご体31の重さによって鍋本体11が倒れないように鍋本体11を片方の手で支持しながら、もう片方の手で脚体41を回動させ、脚体41の中央部をテーブルに載せる。これにより、網かご体31が鍋本体11と脚体41によって支持される。そして、網かご体31の下方のテーブル面に鍋蓋20を、取っ手22をテーブル側に向けた状態で載置する。これにより、網付き鍋1は、図2に示す状態となり、使用者は、網かご体31に入っている蕎麦を食することが可能になる。このとき、茹でた麺からの水滴が網かご体31を通過して落下しても、凹状の鍋蓋20の裏面で水滴を受けることができるため、テーブル等が汚れることを低減することができる。 【0039】 このように構成された本実施形態によれば、鍋本体11の上部に網かご体31が開閉自在に取り付けられ、鍋本体11の開口に網かご体31を被せた閉状態と、網かご体31を開口から離間させて鍋本体11の側方に位置付ける開状態と、に切り替えることが可能になる。これにより、閉状態とすることによって茹でた麺類をこぼすことなく湯切りをすることが可能になり、しかも湯切り後の麺類を鍋本体11から網かご体31に移して開状態にすることによって、網かご体31に麺類を盛り付けることが容易に可能になる。このように、麺類を茹でた際に、より簡単に湯切りをすることが可能になり、湯切りの後の麺類を網かご体31に容易に盛り付けることが可能になる。 【0040】 また、網かご体31は、鍋本体11を被った閉状態において上方に膨出しているため、湯切りをした後、網かご体31が鍋本体11の上方を被った状態を維持しながらひっくり返すことにより、麺類を網かご体31に移動させるとともに、麺類を網かご体31にそのまま保持させることが可能になる。このように、茹で上がった麺類の移動が容易になり、湯切りの後の麺類を網かご体31に容易に盛り付けることが可能になる。 【0041】 また、脚体41を回動させることにより、鍋本体11の側方に位置付けた網かご体31を支持することが可能になる。このため、使用者は、網かご体31に入っている蕎麦を食することが可能になる。 【0042】 以上、本考案の実施形態について説明したが、本考案の実施形態は上述した実施形態に限るものではない。上述した実施形態によれば、鍋本体11及び網かご体31は立方体形状であるが、それ以外の形状であってもよい。例えば、有底の円筒形であってもよい。また、鍋本体の形状に合わせて鍋蓋も円板状であってもよい。 【0043】 また、上述した実施形態によれば、網かご体31の回動を規制するストッパを備えているが、ストッパが複数段階で回動を規制できるようにしてもよい。これにより、例えば、鍋本体11の下に鍋敷きを敷いた場合のように、鍋本体11の位置が若干高くなっても、脚部40をテーブル面に当接させることが可能になり、鍋本体11の側方に位置付けた網かご体31を安定させることができる。 【符号の説明】 【0044】 1 網付き鍋 10 鍋部 11 鍋本体 12 把手 20 鍋蓋 21 蓋体 22 取っ手 30 網部 31 網かご体 32 網把手 33 ヒンジ 40 脚部 41 脚体 42 軸受部 |
【図1】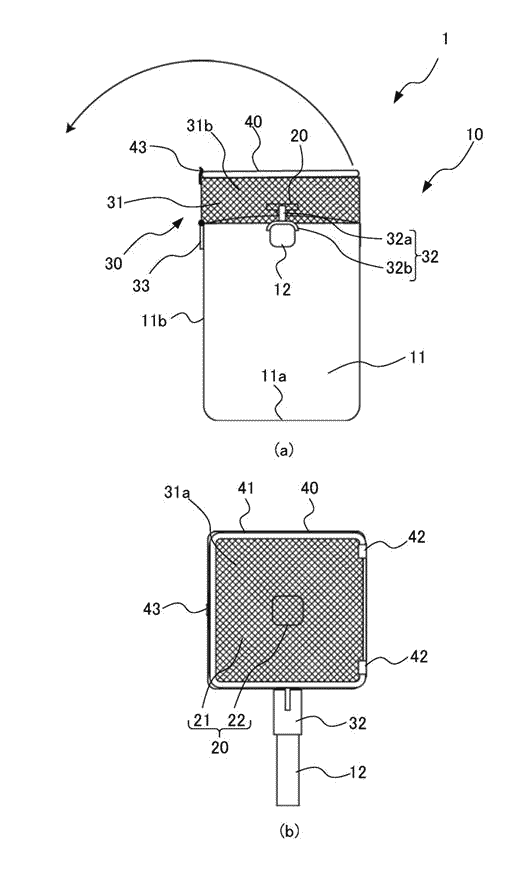 |
【図2】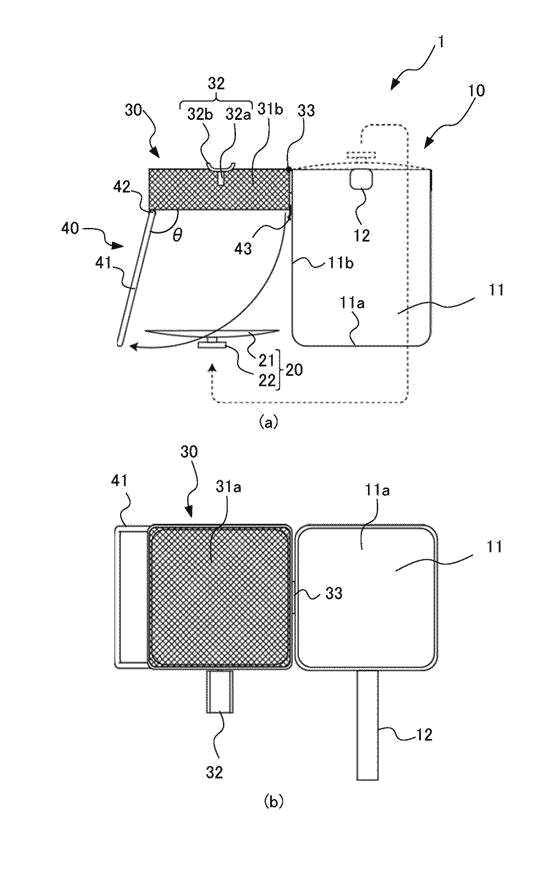 |
ベストキッチン: 細井 網付き鍋仕様書(麺屋) 1.この商品は自宅で簡単に本格的な生メンを調理できる調理器具です。 ①麺業界に革命を起こす衝撃的な鍋登場! ②簡単にプロ並の生麺が調理出来ます! ③従来の麺食を劇的に変え、日本の麺文化を世界に発信します! ④簡単に冷し中華が素早く調理出来ます! ⑤簡単につけ麺が調理出来ます! 2.使用方法 ①鍋に生メンを入れる。 ②沸騰したら火を止め、ザルと鍋の取っ手を持ち逆さにしてお湯を捨てる。 ③別の容器に移す場合は、メンを別の容器に入れる。 ④容器にスープとお湯を入れる。 ⑤そのまま容器として使用する場合は、鍋にメンとスープを入れる。 ⑥お湯の量は内側の目盛りを参考にする。 ⑦具を入れる。 3.その他の用途 ①スパゲッティを調理する場合は多めの水を入れる。 ②メンが適度な硬さになったら火を止める。 ③ザルの水を捨て、そのまま容器として使用する場合は、 メンを鍋に戻しソースをかけ そのまま食べる。 ④蕎麦を調理する場合は同様に沸騰させお湯を捨て、水を流し網にメンを置き、 鍋にメンつゆを入れ食べる。 かけ蕎麦の場合は鍋にお湯とメンつゆを入れ、 メンを入れ、食べる。 ⑤インスタントラーメンもお湯を切ることによって食感が増します。 4.特徴 ①完全に水切りできるため、メンにつゆが染み込みやすい。 ②本格的なラーメン屋の生メンが手軽に調理できる。 ③鍋自体がラーメンどんぶりになる。 ④スパゲッティも簡単に調理できる。 ⑤日本蕎麦も簡単に調理できる。 ⑥そうめん、ひやむぎも簡単に調理でき、そのまま食べられる。 ⑦水切りが良い。 ⑧アウトドア用品として、山や川等のキャンプで本格的なラーメンを味わえる。 |
| 1.Best Kitchen:Hosoi Specifications for pot with net (noodle shop) This product is a cooking utensil that allows you to easily prepare authentic fresh noodles at home. ①A shocking new pot that will revolutionize the noodle industry! ②You can easily cook fresh noodles like a professional! ③Dramatically change the traditional noodle diet and introduce Japanese noodle culture to the world! ④Easy to cook cold ramen quickly and easily! ⑤Easy to cook tsukemen! 2.How to use ①Put fresh noodles in a pot. ②When the water comes to a boil, turn off the heat, hold the colander and the handle of the pot upside down, and discard the water. ③If you wish to transfer the noodle to another container, place the noodle in another container. ④Pour the soup and hot water into the container. ⑤If you want to use it as a container as it is, put the noodle and soup in the pot. ⑥Refer to the scale on the inside for the amount of hot water. ⑦Add the ingredients. 3.Other Uses ① When cooking spaghetti, add more water. ②Turn off the heat when the noodle reaches the proper hardness. ③If you want to use it as a container, return the noodle to the pot, pour the sauce over them, and eat them as they are. ④If you want to cook soba noodles, bring the water to a boil, pour out the water, place the noodles on a net, pour the men-tsuyu into the pot and eat. If you want to eat kake-soba, pour hot water and men-tsuyu into the pot, and eat. ⑤Instant ramen noodles can also be made by draining the water to enhance their texture. 4.Features ①Because the water can be drained completely, the noodle can soak up the broth easily. ②Easy to prepare authentic fresh noodles of professional ramen shops. ③The pot itself can be used as a ramen bowl. ④Spaghetti can be easily cooked. ⑤Japanese buckwheat noodles (soba) can be easily cooked as well. ⑥Somen (Japanese thin wheat noodles)and hiyamugi (cold soupy noodle) can be easily cooked and eaten as they are. ⑦Easy to drain. ⑧Can be used as outdoor equipment for camping in the mountains or rivers, etc. |
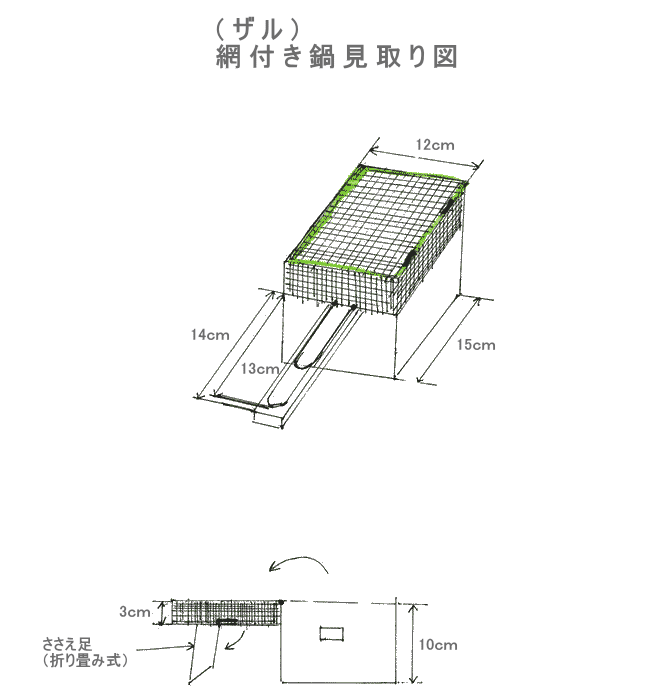 |
| ページtop へ |