| 閉じる |
| 【発明の名称】歩行姿勢確認具および靴 【特許権者】 【識別番号】511083008 【氏名又は名称】吉岡 久光 【住所又は居所】東京都渋谷区西原1―14―10 【代理人】 【識別番号】110001494 【氏名又は名称】前田・鈴木国際特許弁理士法人 【発明者】 【氏名】吉岡 久光 【住所又は居所】東京都渋谷区西原1―14―10 【参考文献】 【文献】 国際公開第2019/040797(WO,A1) 【文献】 特開平10−066604(JP,A) 【文献】 米国特許第02413545(US,A) 【文献】 実公昭50−026513(JP,Y1) 【特許請求の範囲】 【請求項1】 板片形状であって、長手方向が足の長さ方向に交差するように配置され、短手方向に沿う断面が上に凸の樋状であり、上方からの踏み込み荷重により前記長手方向の中央部が下方に曲がり、前記踏み込み荷重が無くなると前記長手方向に関して直線状に戻るように弾性変形して振動や音が歩行者に伝えられる弾性板状部材と、 前記弾性板状部材がソールにおける踵位置から逸脱しないように、かつ、前記弾性板状部材を前記ソールに対して固定せずに、前記弾性板状部材を保持する保持部材と、を有する歩行姿勢確認用具。 【請求項2】 前記弾性板状部材は、金属性であることを特徴とする請求項1に記載の歩行姿勢確認用具。 【請求項3】 前記弾性板状部材の前記長手方向の前記中央部に対して一方側と他方側とに、互いに間隔を空けて配置されており、前記弾性板状部材と前記ソールとの間に設けられる一対の支え部材を、さらに有する請求項1または請求項2に記載の歩行姿勢確認用具。 【請求項4】 前記保持部材は、前記弾性板状部材の前記長手方向の前記中央部に対して一方側に配置されており、前記弾性板状部材の上面に沿って前記弾性板状部材の前記短手方向に架け渡されて、前記弾性板状部材の一方側を規制する第1保持部材と、 前記弾性板状部材の前記長手方向の前記中央部に対して他方側に配置されており、前記弾性板状部材の前記上面に沿って前記弾性板状部材の前記短手方向に架け渡されて、前記弾性板状部材の他方側を規制する第2保持部材と、を有する請求項1から請求項3までのいずれかに記載の歩行姿勢確認用具。 【請求項5】 請求項1から請求項4までのいずれかに記載の歩行姿勢確認用具を、前記ソールの前記踵位置に備える靴。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 【0001】 本発明は、躓きにくい歩行姿勢を自分で確認することができる歩行姿勢確認用具よびこれを備える靴に関する。 【背景技術】 【0002】 自分の歩行姿勢を客観的に確認する方法には、他人に助言をもらうか、鏡に写すか、ビデオ等の映像によって確認する方法がある。しかしながら、これらの方法では、いつも確認しながら歩行することは難しく、適切な歩行姿勢を維持することが難しいという問題がある。 【0003】 ここで、歩行中に、自ら歩行姿勢を確認可能な歩行姿勢確認用具として、本発明の発明者による特許文献1に記載の技術が提案されている。この技術は、歩行中に歩行者自身が、みずからの歩行姿勢が適切であることを確認可能である。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0004】 【特許文献1】 特開2013−165943号公報 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 しかしながら、従来の歩行姿勢確認用具では、パイプ内に入った球体が移動するものであるため、慣性に抗して動く球体の円滑な移動を制御・維持することが難しく、耐久性およびメンテナンス性の観点で課題があった。 【0006】 本発明は、上述のような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、より簡素な構造で耐久性およびメンテナンス性に優れた歩行姿勢確認用具を提供することである。 【課題を解決するための手段】 【0007】 本発明に係る歩行姿勢確認用具は、 板片形状であって、長手方向が足の長さ方向に交差するように配置され、短手方向に沿う断面が上に凸の樋状であり、上方からの踏み込み荷重により前記長手方向の中央部が下方に曲がり、前記踏み込み荷重が無くなると前記長手方向に関して直線状に戻るように弾性変形する弾性板状部材と、 前記弾性板状部材がソールにおける踵位置から逸脱しないように、かつ、前記弾性板状部材を前記ソールに対して固定せずに、前記弾性板状部材を保持する保持部材と、を有する。 【0008】 本発明に係る歩行姿勢確認用具は、ソールの踵位置に配置される弾性板状部材が、歩行時の踵位置への踏み込み荷重により変形することにより、弾性板状部材の変形時の振動や音が歩行者に伝えられ、歩行者自身が、歩行中に、踵から踏み込む適切な歩行姿勢で歩けているかどうかを確認できる。また、本発明に係る歩行姿勢確認用具は、弾性板状部材の変形を利用しているため、パイプ内の球体の動きを利用した従来技術に比べて構造が簡素であり、耐久性およびメンテナンス性に優れている。また、弾性板状部材が歩行者の踵の下に配置されるため、歩行時に意識すべき歩行者の踵に対して、良好に弾性板状部材の振動が伝わる。そのため、このような歩行用姿勢確認用具は、確認機能の観点でも、従来の歩行姿勢確認用具に比べて優れている。また、保持部材が弾性板状部材をソールに対して固定しないので、保持部材が弾性板状部材の変形を阻害する問題を防止でき、また、保持部材の固定部分から弾性板状部材の損傷や劣化が生じる問題を防止できる。 【0009】 また、たとえば、前記弾性板状部材は、金属性であってもよい。 【0010】 弾性板状部材は、変形時に振動を生じる適切な硬さを有する任意の材質とすることができるが、金属性とすることが、耐久性等の観点から好ましい。 【0011】 また、たとえば、本発明に係る歩行姿勢確認用具は、前記弾性板状部材の前記長手方向の前記中央部に対して一方側と他方側とに、互いに間隔を空けて配置されており、前記弾性板状部材と前記ソールとの間に設けられる一対の支え部材を、さらに有してもよい。 【0012】 このような支え部材は、弾性板状部材の中央部とソール間に隙間を形成することにより、弾性板状部材の踏み込み荷重による円滑な変形を促すことができる。 【0013】 また、たとえば、前記保持部材は、前記弾性板状部材の前記長手方向の前記中央部に対して一方側に配置されており、前記弾性板状部材の上面に沿って前記弾性板状部材の前記短手方向に架け渡されて、前記弾性板状部材の一方側を規制する第1保持部材と、 前記弾性板状部材の前記長手方向の前記中央部に対して他方側に配置されており、前記弾性板状部材の前記上面に沿って前記弾性板状部材の前記短手方向に架け渡されて、前記弾性板状部材の他方側を規制する第2保持部材と、を有してもよい。 【0014】 このような保持部材は、保持部材が弾性板状部材の変形を阻害する問題をより確実に防止でき、また、保持部材の固定部分から弾性板状部材の損傷や劣化が生じる問題も確実に防止できる。 【0015】 また、本発明に係る靴は、上記いずれかに記載の歩行確認用具を、前記ソールの踵位置に備える。 【0016】 本発明に係る靴は、上記のような歩行確認用具を、前記ソールの踵位置に備えるため、本発明に係る靴を履いて歩行することにより、歩行者自身が、自分の歩行姿勢が適切であるか否かを、容易に確認することができる。 【図面の簡単な説明】 【0017】 【図1】図1は、本発明の一実施形態に係る靴およびソールの踵位置に備えられる歩行姿勢確認用具を示す概略図である。 【図2】図2(a)は、図1に示す歩行姿勢確認用具およびその周辺部の平面図、図2(b)は図2(a)に示す歩行用確認用具に含まれる弾性板状部材の短手方向に沿う断面図である。 【図3】図3は、図2に示すIIIーIII線に沿う断面図であり、歩行姿勢確認用具を後方から見た概念図である。 【図4】図4は、歩行姿勢確認用具が踏み込み荷重により曲げられた状態を示す概念図である。 【図5】図5は、歩行姿勢確認用具が図4に示す状態から直線状の状態に戻った状態を示す概念図である。 【図6】図6は、歩行姿勢確認用具を備える靴を履いて歩行している歩行者を示す概念図である。 【図7】図7は、図6に示すそれぞれの歩行状態における歩行者の足元を拡大して示す拡大図である。 【発明を実施するための形態】 【0018】 図1は、本発明の一実施形態に係る靴60およびソール62の踵位置62aに備えられる歩行姿勢確認用具10を示す概略図である。図1に示すように、歩行姿勢確認用具10は、ソール62における踵位置62aに設置して使用される。 【0019】 歩行姿勢確認用具10を設ける踵位置62aは、ソール62において、靴60を履いた人の足90(図4、図5参照)の踵の下になる部分であり、土踏まず位置62cより靴60のつま先60aから遠い部分である。なお、歩行姿勢確認用具10は、ソール62の上(ソール62と足90の間)に設けられてもよいが、インソールの下などのソール62の内部に設けることも可能である。 【0020】 図1に示すように、歩行姿勢確認用具10は、板片形状である弾性板状部材20と、弾性板状部材20を保持する保持部材30とを有する。また、歩行姿勢確認用具10は、弾性板状部材20とソール62との間に設けられる一対の支え部材40を有する。なお、靴60および歩行姿勢確認用具10の説明においては、靴60のソール62からアッパー64へ向かう上下方向をZ軸方向、靴60のつま先60aから踵へ向かう方向をY軸方向、Z軸方向およびY軸方向に直交する方向をX軸方向として説明を行う。 【0021】 図2(a)は、図1に示す歩行姿勢確認用具10を上方(Z軸正方向)から見た平面図であり、図2(b)は、歩行姿勢確認用具10における弾性板状部材20の短手方向に沿う断面図である。弾性板状部材20は、平面視略矩形の板片形状であり、互いに略平行な一対の長辺28と、2つの長辺28を接続する一対の短辺26を有する。図2(a)に示すように、弾性板状部材20の短辺26の一方または両方の一部または全部には、後方に向かってX軸中央方向に傾斜する傾斜部26aが形成されていてもよい。このような傾斜部26aを形成することにより、弾性板状部材20をソール62の後端(Y軸正方向側)に近づけて配置することができる。弾性板状部材20をソール62の後端に近づけて配置することにより、正しい歩行姿勢で踵から着地したときにのみ、変形に伴う振動と音を弾性板状部材20に生じさせることができる。 【0022】 図1および図2(a)に示すように、弾性板状部材20は、長手方向(長辺28が伸びる方向)が足の長さ方向(Y軸方向)に交差するように配置される。また、図2(b)に示すように、弾性板状部材20は、短手方向(長辺28が伸びる方向に垂直な方向、X軸方向)に沿う断面が上に凸の樋状であり、短手方向に関して湾曲する湾曲形状を有する。 【0023】 図2(a)に示すように、保持部材30は、弾性板状部材20がソール62における踵位置62aから逸脱しないように、弾性板状部材20を保持する。図3は、図2に示すIIIーIII線に沿う断面図であり、歩行姿勢確認用具10を後方から見た概念図である。 【0024】 保持部材30は、弾性板状部材20の長手方向(X軸方向)の中央部20cに対して一方側(X軸負方向側)に配置されており弾性板状部材20の一方側20aを規制する第1保持部材32と、弾性板状部材20の長手方向(X軸方向)の中央部20cに対して他方側(X軸正方向側)に配置されており弾性板状部材20の他方側20bを規制する第2保持部材34とを有する。第1保持部材32および第2保持部材34は、ひも状または糸状の部材であるが、保持部材30としてはこれらのみには限定されない。 【0025】 図2(a)に示すように、第1保持部材32は、弾性板状部材20の上面22に沿って弾性板状部材20の短手方向(Y軸方向)に架け渡されており、弾性板状部材20の一方側20aを保持する。図2(a)および図3に示すように、第1保持部材32の両端は、支え部材40を貫通してソール62に固定されている。ただし、第1保持部材32の両端は、支え部材40に固定されていてもよい。 【0026】 第2保持部材34は、第1保持部材32と同様に、弾性板状部材20の上面22に沿って弾性板状部材20の短手方向(Y軸方向)に架け渡されており、弾性板状部材20の他方側20bを保持する。図2(a)および図3に示すように、第2保持部材34の両端は、支え部材40を貫通してソール62に固定されている。ただし、第2保持部材34の両端は、支え部材40に固定されていてもよい。 【0027】 第1保持部材32と第2保持部材34とを有する保持部材30は、弾性板状部材20をソール62に対して固定せずに保持する。すなわち、第1保持部材32と第2保持部材34とは、弾性板状部材20の上面22に接触しているだけで、弾性板状部材20に固定されていないため、弾性板状部材20の変形をほとんど妨げない。ただし、弾性板状部材20は、ソール62における踵位置62aから逸脱する動きや、長手方向の向きがY軸方向に平行になるように大きく回転する動きについては、このような動きを行わないように、保持部材30によって規制される。保持部材30自体は、ゴムやエラストマのように伸縮性を有していてもよいが、鋼線や紐のように伸縮性を有しなくてもよい。なお、保持部材30自体が伸縮性を有する場合は、保持部材30が弾性板状部材20に対して接続・固定されていてもよい。 【0028】 図2(a)および図3に示すように、一対の支え部材40は、弾性板状部材20の長手方向の中央部20cに対して一方側(X軸負方向側)と他方側(X軸正方向側)とに、互いに間隔を挙げて配置される。支え部材40が、弾性板状部材20とソール62との間に間隔を空けて配置されることにより、弾性板状部材20の中央部20cとソール62における踵位置62aの上表面との間に隙間46が形成される。このような支え部材40は、後述する踏み込み荷重による弾性板状部材20の円滑な変形を促すことができる。 【0029】 ただし、支え部材40の厚みは特に限定されず、0.2〜3.0mm程度とすることができる。また、ソール62が柔軟な材質である場合は、隙間46を形成しなくても踏み込み荷重による弾性板状部材20の適切な変形が生じる場合があり、そのような場合は、支え部材40は省略可能である。 【0030】 図4および図5は、歩行姿勢確認用具10の使用時の変形を説明する概念図であり、図4は、歩行姿勢確認用具10が踏み込み荷重により曲げられた状態を示しており、図5は、図4に示す状態から図3等に示す直線状の状態に戻った状態を示している。また、図6は、図1に示す靴60を履いた人が歩行する状態を示しており、図7は、図6に示す各歩行状態における左足を拡大して表示したものである。以下、図4〜図7を用いて、歩行姿勢確認用具10の構造および動作について、さらに説明を行う。 【0031】 図6(a)および図7(a)に示す歩行者の左足に着目すると理解できるように、靴60を履いた歩行者が、躓きにくいて適切な歩行姿勢で歩く際には、靴60における踵側から地面に着地する。次に、図6(b)および図7(b)並びに図6(c)および図7(c)に示すように、左足の踵からつま先に体重移動しながら右足を前に振り出し、次に右足を踵から着地させる。 【0032】 図6(a)および図6(b)並びに図7(a)および図7(b)に示すように、正しい歩行姿勢で歩くと、踵に体重が乗る状態が生じる。図4は、踵に体重が乗った状態における靴60内部の歩行姿勢確認用具10を示している。図4に示すように、弾性板状部材20は、足90による上方からの踏み込み荷重により、長手方向(X軸方向)の中央部20c(図3参照)が下方に曲がるように変形する。 【0033】 これにより、図3に示すような踏み込み荷重が作用しない状態で直線状であった弾性板状部材20の長辺28は、踏み込み荷重により湾曲する。なお、図4では図示していないが、中央部20cが下方に曲がるのに併せて、拘束されていないX軸方向の両端部が上方に移動し、弾性板状部材20は、図4に示す状態より深い湾曲形状となる場合がある。 【0034】 また、図6(c)および図7(c)に示すように、正しい歩行姿勢で歩くと、踵に体重が乗らない(または踵が浮く)状態も、踵に体重が乗る状態と交互に生じる。図5は、踵に体重が乗らない(または踵が浮く)状態における靴60内部の歩行姿勢確認用具10を示している。 【0035】 図5に示すように、弾性板状部材20は、足90によるからの踏み込み荷重が無くなることにより、図4に示すような曲げが解除され、長手方向(X軸方向)に関して直線状に戻るように弾性変形する。このように、弾性板状部材20は、歩行者の適切な姿勢による歩行に合わせて変形を繰り返し、変形による振動と音を生じる。 【0036】 図4および図5に示すように、弾性板状部材20は、足90の踵の近くに配置されているため、特に弾性板状部材20の振動が足の踵に効果的に伝わり、これにより歩行者は、自分が正しい姿勢で歩行できていることを認識できる。また、弾性板状部材20が上に凸となる樋状であり上面22が滑らかであるため、非歩行時に感じる違和感も少ない。なお、歩行者が、前傾姿勢でつま先から着地するような躓きやすい歩行姿勢で歩いている場合には、弾性板状部材20は上述したような変形を生じない。 【0037】 歩行姿勢確認用具10は、弾性板状部材20の変形を利用しているため構造が簡素であり、耐久性およびメンテナンス性に優れている。弾性板状部材20が歩行者の踵の下に配置されるため、歩行時に意識すべき歩行者の踵に対して、良好に弾性板状部材の振動が伝わるため、歩行者に適切な歩行姿勢を維持するように促す効果も期待できる。 【0038】 弾性板状部材20の材質としては、上述したような弾性変形を行うことができる金属、樹脂などが挙げられるが、弾性板状部材20は、金属性であることが、耐久性などの観点から好ましい。また、弾性板状部材20の材質は、鉄鋼、ステンレス鋼であることが、これらが靭性に富むことから好ましい。 【0039】 弾性板状部材20の厚み(板材の厚み)は、たとえば0.05〜2mm程度とすることができるが、特に限定されない。図2(b)に示す弾性板状部材20の湾曲高さは、特に限定されないが、たとえば0.5〜4mm程度とすることができる。また、図2(a)に示す弾性板状部材20の長辺方向(X軸方向)の長さは、靴のサイズにもよるが、25〜75mm程度とすることができる。弾性板状部材20の短手方向(Y軸方向)の長さは、たとえば、4〜30mm程度とすることができる。 【0040】 図1では、左足用の靴60のソール62に、歩行姿勢確認用具10を備える実施形態を例に挙げて説明を行ったが、歩行姿勢確認用具10は、両足の靴にそれぞれ備えられることが好ましい。ただし、歩行姿勢確認用具10は、片足の靴のみに備えられていてもよい。 【0041】 以上、実施形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態のみに限定されるものではなく、他の実施形態や変形例を有することは言うまでもない。たとえば、保持部材は、伸縮性のある粘着テープ等で構成されており、ソール62の上面に固定されていてもよい。また、支え部材40は、粘着テープや接着によりソール62に固定されてもよい。 【符号の説明】 【0042】 10…歩行姿勢確認用具 20…弾性板状部材 20a…一方側 20b…他方側 20c…中央部 22…上面 26…短辺 28…長辺 30…保持部材 32…第1保持部材 34…第2保持部材 40…支え部材 46…隙間 60…靴 60a…つま先 62…ソール 62a…踵位置 62c…土踏まず位置 64…アッパー 90…足 |
歩行姿勢確認【躓き転倒防止靴】 ズッカナイト 躓かないインソールの靴 最近中高年者の躓き転倒が問題になっております。 股関節脱臼から転倒骨折をしてしまい転倒の恐怖から外出をしなくってしまい私の妹に歩ける靴を考えておりました。 色々な方の歩きか方をモデルに爪先が上がり踵から着地出来る靴の試作を続け、専門家のアドバイスやお力添えもあって躓かない装置(歩行姿勢確認具)を造り上げる事が出来ました。 この装置は、インソールの踵部分に設置した装置から発生する沈み込む音と振動が装着者に伝わる仕組みです。 この正しい歩行姿勢を音と振動を感じながら歩き、この音と振動が無ければ躓く危険を知らせるのです。 爪先が上がり踵からの着地を音と振動を確認しながら歩けるのです。 家族や付き添い者にもこの音が安心を伝え、聞こえなくなった時が躓く危険を本人に知らせる事が出来るのです。 この装置は、何の動力も不要で重量も約5グラムと軽く負担にはなりません。それに半永久的に使用可能です。 躓き防止の同じような踵からの歩行装置のアメリカから拒絶通知がありましたが特許庁は拒絶理由にならないとの対応で難無く無事に特許取得となりました。 特許第7626438号 拒絶通知のこのアメリカの企業も、日本での販売を企んでいたものと推察いたします。 是非日本だけでなくアメリカでの販売と他、各国での販売が可能ではないかと思われます。 優れたスニーカー製作会社に使って欲しいものです。 インソールにこの装置を設置したスニーカーと特許書類と図面写真も合わせて持参いたしますので是非ご検討をお願いいたします。 ズッカナイト 吉岡久光 hisamitsu.yoshioka@gmail.com |
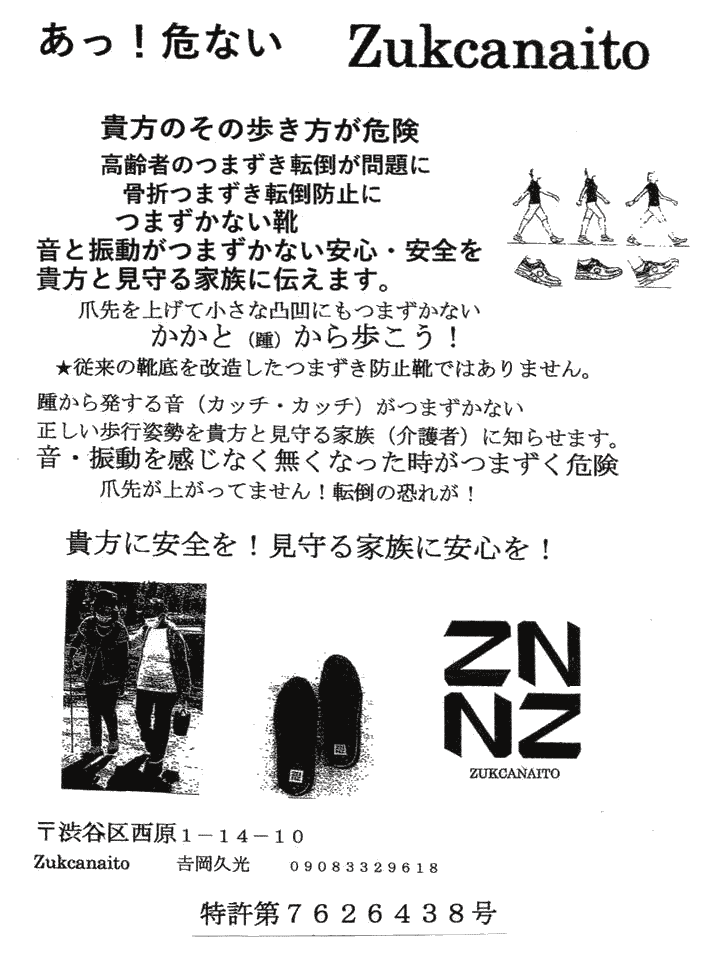 |
【図1】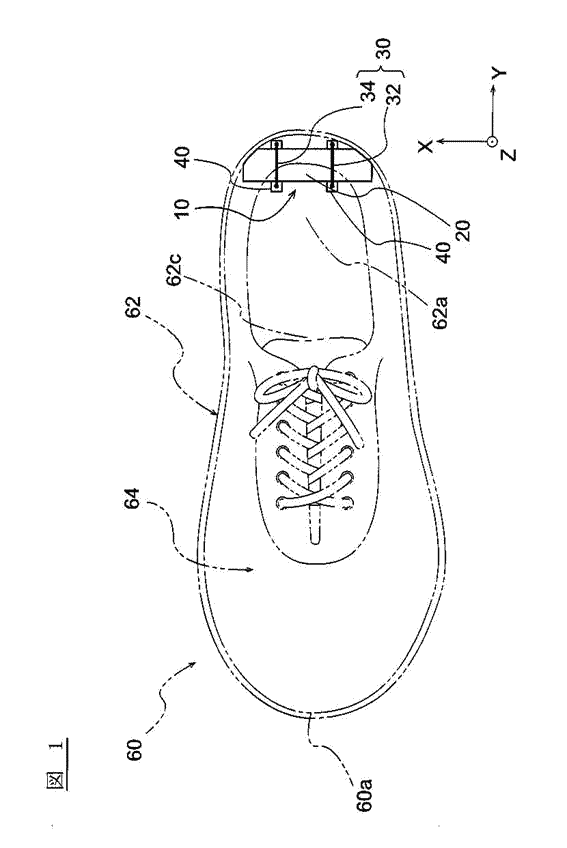 |
【図2】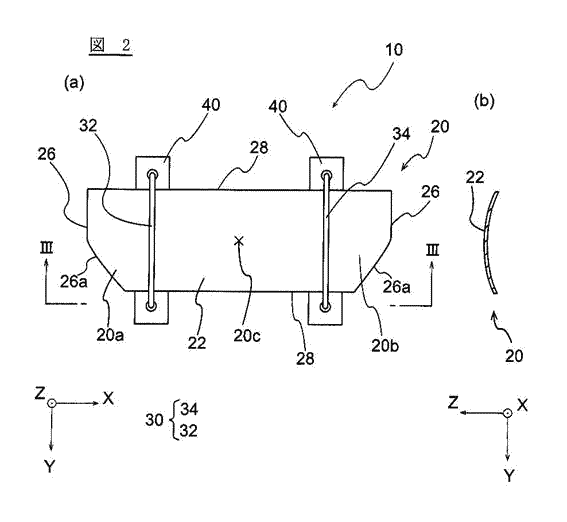 |
【図3】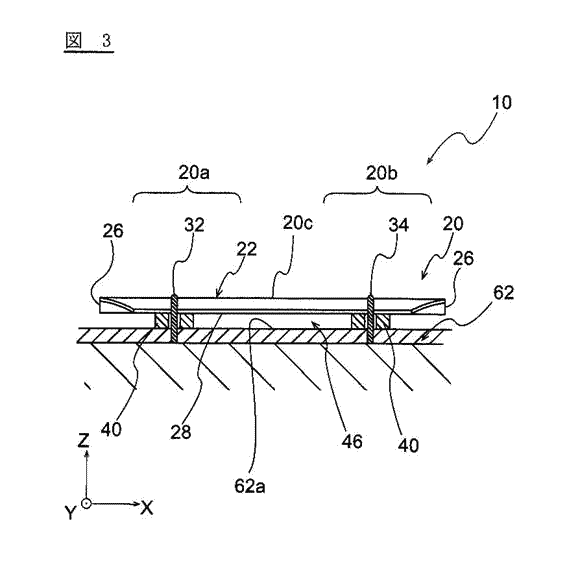 |
【図4】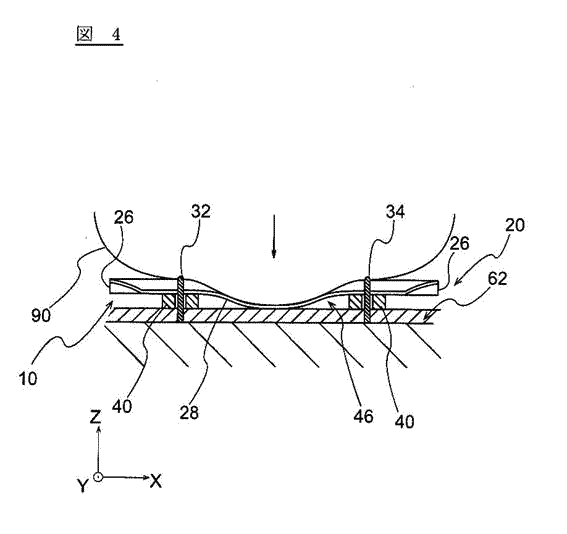 |
【図5】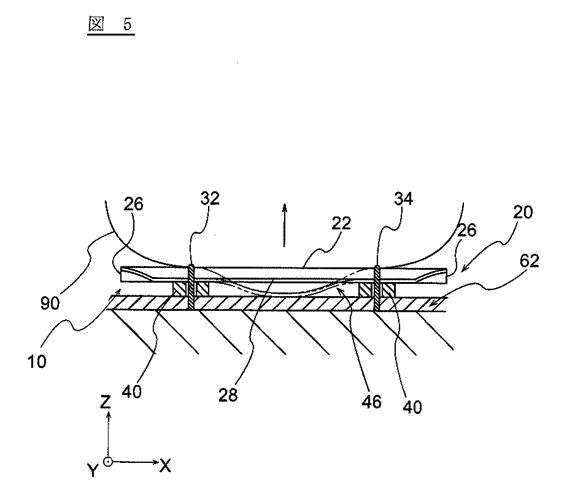 |
【図6】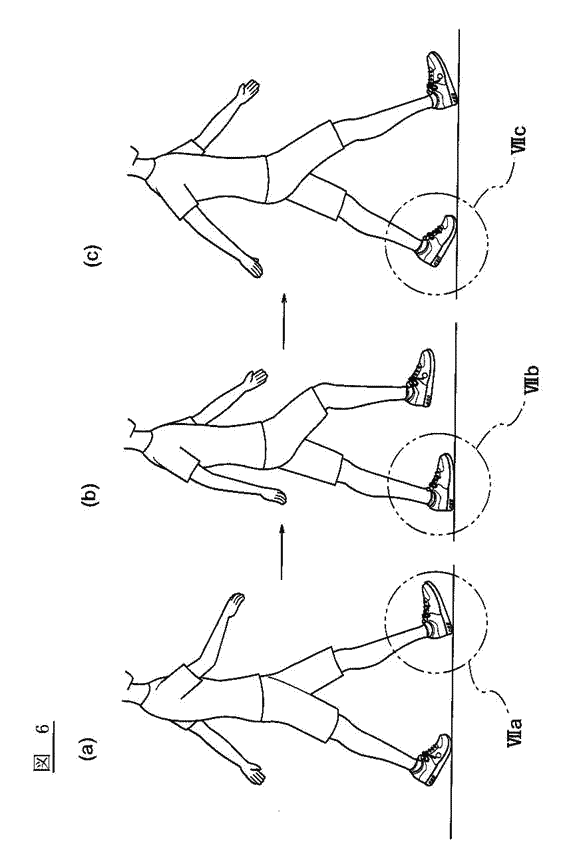 |
【図7】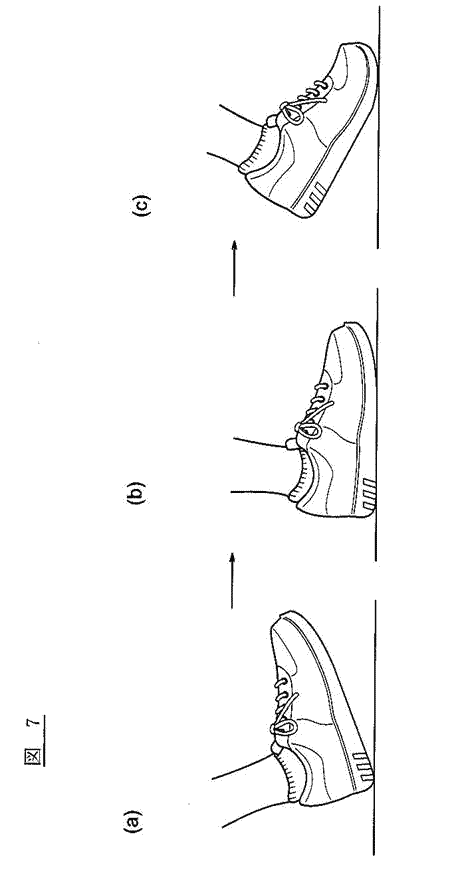 |
| ページtop へ |